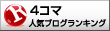【お知らせ】
あすぺさん本☆第2弾「発達障害 工夫しだい 支援しだい」
発売情報はこちら→記事:【お知らせ】あすぺさん本の第2弾がでます♪
今日は、よく使われる「あいまい言葉」についてのお話です。
最近、ある人と「○時過ぎ」に待ち合わせをしました。
私は、○時5分前に待ち合わせ場所について待っていました。
○時ちょうど。まだ来ません。
まぁ、「過ぎ」ですから、ちょうどよりは後ということですもんね。うん。
○時5分。まだ来ません。
まぁ、「過ぎ」って言うぐらいですから、5分すぎてからだよね。そろそろだねー。
○時10分。まだ来ません。
そろそろかなーと思うんだけど…。
○時15分。まだ来ません。
まだ?!
なんぼ「過ぎ」って言っても、15分も過ぎたら、過ぎすぎやろーっ(怒)
結局、○時17分ごろに相手の方は来られました。
ところが、まったく気にしている風もないところを見ると、本人的には「遅れた」という意識もないようです。つまり、本人的には「○時過ぎ」=「○時15分ごろ」という意味だったようです。
ちなみに、以前この人と○時30分で待ち合わせをした時、私が余裕を見て乗ったにもかかわらず、電車の延着で約束の時間に2分ほど遅れた時には、モーレツに不快な表情をしてました…。(理由を言ったら納得されましたが。)そんな方ですから、自分が遅れて知らん顔ということはないでしょう。
そう考えると、15分ごろというのが、この人の考える「○時過ぎ」なのでしょう…。
そこで、ふと「○時過ぎ」って、何分ごろのことを言うのだろう?と疑問に思ったのです。
私の中での「○時過ぎ」の定義は、○時5分~10分ぐらいでした。
で、インターネットで検索してみました。
・「〇時過ぎ」という表現ですが、「過ぎ」とは何分までを指すのですか?
・3時過ぎって何分までですか?
これを見ると、人によって、かなり定義がばらつきますね。
私と同じ5~10分という人もいれば、15分ごろ、30分までOKなどなど…。
不思議です!!!
これだけ個人の感覚でばらつきがあるにもかかわらず、みんな黙ってやり過ごしているわけですから…。しかも、微妙に不満をためながら…。
○時過ぎについて定義が違う人が、○時過ぎって約束するたびに、待たされる方には、小さな不満がたまります。しかも、遅れてきた方は、「遅れた」意識も「待たせた」意識もないので平然としています。
気づかないうちに、相手を不快にしているんですよね。
(↑まぁ、発達障害の人の場合は、よくある話ですが…(笑))
ところで、私は、あいまいな言葉に対しては、自分なりの基準を決めて、それにしたがって自分なりの定義を作っていることが多いです。
もちろん、私は「○時過ぎ」に15分や30分というのが範囲に含まれないと考える理由もきちんとあります。
「○時過ぎ」という表現は、あくまでも「○時」=「○時00分」を基準にして、○時00分から「過ぎた時刻」と考えているから。(「○時過ぎ」の「○時」は「○時の時間帯」という意味では捉えていないのです。)
つまり、○時00分を基準にして表現するということは、00分から大きくかけ離れた時間ではおかしい。大核かけ離れるなら、もはや00分を基準にすることに意味がないですから。もっと、近い時刻を基準にすればいいわけです。
ここで、私の中での「大きくかけ離れる」の基準は、1時間の4分の1(=15分)です。全体の4分の1は、私の中ではもはや「誤差」や「少量」ではないからです。ですから、私の中では、1時間の4分の1(=15分)も離れるんなら、○時15分と表現すべき、と考えているわけです。
そうすると…
「○時過ぎ」の表現は、15分以下。「過ぎ」というあいまい表現を使うのは"大さっぱな時刻"の指定という意味ですから、時計の大きいメモリの単位で数えます。すると、15分以下の大きいメモリだと、10分が限界。
もちろん、「過ぎ」ですから、00分ちょうどは含まれません。大きいメモリ1つ分=5分からが範囲になるかな…と。
…という考えで「○時過ぎ=○時5~10分」と考えていました。
同じ論理で「○時前」は○時の5~10分前だと考えています。
私自身が、わざわざ「○時過ぎ」という言葉を選択する場合には、「○時ちょうどっていうほど、厳しくは指定しないけど、その時間めざして来てね」というニュアンスを含めて使っていました。
あまりにも、かけ離れた「○時過ぎ」の解釈を知って、今後は、使わないようにしようと思いました…。だって、こちらの含めたニュアンスが伝わる確証がない上に、相手の定義と違っていると、内心で不満をためてしまうことになりますから…。
もちろん、私の定義が正しいか誤っているかという議論は、まったく意味がありません。そもそも、「正解」がない問題ですから。
あいまい言葉は、自分の解釈・定義が大多数の人と一致するかどうかが問題なんですよね。このあたりも、発達障害の感じ方に対する問題と非常に共通する部分があります。
この社会では、「少数派の行動」=「非常識」「不正解」とされてしまうということ。
つまり、単なる数の問題で決められている「非常識」「不正か」という判定は、たいした根拠がないわけです。そう考えると、「常識」にとらわれてがんじがらめになるのは、ばかばかしいことに思えますね。
とは言っても、現実には無視するわけにもいきません。
ただ、「○時過ぎ」という言葉のように、人によって受け取る意味がかなり異なる言葉の場合は、少なくとも、大切な状況やビジネスの場では、こうしたあいまい言葉を使わないようにすることで回避するしかありませんね。
もし、「○時過ぎ」と指定されたら、「過ぎですかぁ…。じゃぁ、○時10分ぐらいに行くようにしますね。」と、こちらから時刻を宣言しちゃいましょう。
みなさんは、「○時過ぎ」って何分ごろだと思ってました?
周囲の人と話をしてみると、意外に驚く答えが返ってくるかもしれませんよ。(ついでに、意図せず与えていた誤解もとけるかも…?!)