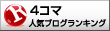【お知らせ】うさぎさんの家族募集の経過報告
先日、ふしみんさんのウサギさんをもらっていただける人を募集したところ…
一羽をのぞく赤ちゃんウサギさんの家族が決まりました!ありがとうございました(^▽^)/
最後の赤ちゃんウサギは、少し体の調子が悪いので、安定するまでしばらくは、ふしみんさんが育てるそうです。あとは大人のうさぎさんの家族募集ついては、来週に詳細報告できそうです!!
うさぎさんの家族になってくださった方へ。大切に育ててあげてくださいねー(^▽^)(うらやましい。)
------
前回「私の人生を変えた言葉(1)」からの続きです。
アホな私のために丁寧に説明してくれたM先生への申し訳なさで、しょんぼりしてしまった私。
そんな私に、M先生が言ったのは
「お前が理解できへんのは、オレの説明が悪いからや。(きっぱり)」
しかも、なぜか自信たっぷりに。
「ええええっ?!先生、何いってんのー?!」って、めちゃくちゃびっくりしました。
だってね。
今までの人生で、人にいろいろなことを教わってきたし、説明されることがありました。
でも、説明がわからなくて、困った顔をした時に、言われた言葉って、
「わからん?」(困惑)
「なんで、わからんの?」(怒り)
「わからんのやったら、しゃーないな」(あきらめ)
「まぁ、そのうちわかるようになるよ」(なぐさめ)
「いや、できるって…」(顔を引きつらせながら、その場しのぎ的に)
これらの言葉の大前提は
「私の説明がわからないのは、あなたの能力不足」
ということ。
つまり、(言っている本人が無意識でしょうけれど)、説明した側の問題ではなく、「理解できない側」の問題として扱っているわけです。
できないことが多かった私は、こうした言葉をかけられ続けて育ちました。
当然、このときも、「まぁ、そのうちわからうようになるよ」とか、嘘がみえみえの「いやいや、がんばればできるって」という言葉が返ってくるものだとばかり思っていました。
ところ、M先生は、まるで当たり前のことのように、「オレの説明が悪いからやん。」と、自信たっぷりに言い放ったのです。かなり「自信たっぷり」な態度で。(←これがポイントだったと思う。)
しかも、
「オレがお前の年の頃に理解できたことやで?お前が理解できへんわけないやん。」
と、私の能力の問題ではないというのです。
でも、M先生は公立高校から現役で超エリート大学の理系に合格した頭脳の持ち主。(当時は大学院生でアルバイトとして塾の先生をしていました。)
私「だって、先生は、めっちゃ頭ええやん。私と脳みそがちがうよ…」
M先生「あほー。お前かて、進学校の生徒やないか。そんなに脳みそに違いがあるわけないやろ。」
私「…そっか…な」
M先生「そうや。ということは、お前が理解できへんのは、オレの説明が悪いからやないか。へへん!反論できまい(笑)」
もちろん、人には素養というものがあるので、M先生と同じようになれるわけではないことはわかっていました。それでも、「そんなに脳みそに違いがあるわけない」という根拠とともに私の可能性を示してくれたことが、とてもうれしかったです。
ちなみに、根拠のないカラ元気的な「できるよ」は、ただの慰めや、悪い雰囲気のその場しのぎの嘘にしか聞こえませんからね。そんな風に、気を使っている相手を見て、余計に落ち込んでしまいます。
たとえ、M先生と同じ台詞だったとしても、あたかもこちらの顔色を伺って、慰めるような態度で「いや、いや、オレの説明が悪かったんだよ…(汗)」という取り繕うような態度であったなら、私は傷ついていたと思うのです。
自信たっぷりに当然のことといわんばかりの態度で、「オレの説明が悪いに決まってるだろー。なにいってんだー?」と言ったM先生の"本物の"気遣いが、何よりも私にはうれしかったのです。
そして、
「お前には理解できる能力はあるんだ」と信じてくれたことが。
「説明を変えれば、理解できる道がある」と示してくれたことが。
そして、この後、もう一度、先生に説明をしてもらって、しっかり理解できました!
もし、このときに否定的な言葉をかけられていたら、理解をあきらめていたかもしれません。つまり、M先生の言葉が、私の能力を引き出したわけです。
多くの教師が「理解できない」のは「生徒の努力不足」「生徒のやる気の問題」「生徒の能力の低さ」と、生徒の責任にしています。少なくとも、私はM先生に出会うまで、私が理解できなかった時に、「自分の説明が悪い」と断言した先生はいませんでした。
今考えれば、こうした周囲の人の言葉や態度をうけるたびに、私は「やっぱり、私はだめなんだ…」と、自分の評価を下げていました。そして、いつしか「どうせ、やってもムダ」という無力感へと代わり、自らが周囲の言葉どおりに「自分の能力を潰していた」時期もありました。
確かに、発達障害は能力の偏りがあって「フツウ」の方法ではできないことがあるのは事実です。
けれど、こうした否定的な言葉によって、ほんとうは「がんばれば」できることも、「どうせ私はできない」とあきらめてしまったために、できるようになるチャンスを失ってしまったこともあると思うのです。( もちろん、ここで言う「がんばる」とは、「フツウ」のやり方で闇雲に続けるという意味ではなく、「他の方法」を模索して目的を達成するという意味です。)
「私には、なんの取柄も得意もない…」と嘆いてる人の多くが、実はこのタイプなんじゃないかと考えています。
このとき以来、私は、
「相手が理解できないのは、自分の説明が悪いから」
を常に自分の戒めの言葉として持ち続けています。
そのことが、その後の私の人生で、どんな風に役立ったのでしょうか?
次回 [1/17(火)] に続きます。